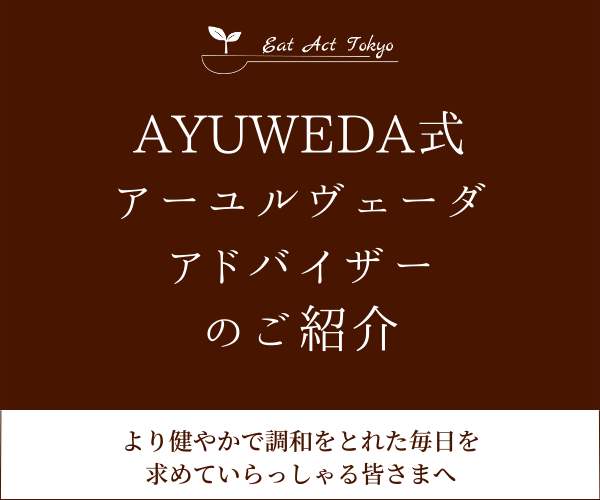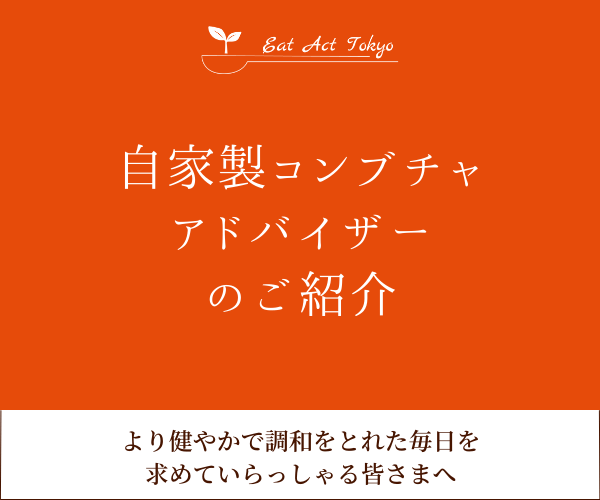今回は、自然にそった暮らし、七十二候の第十八候「牡丹華」について。
牡丹華は、「ぼたんはなさく」と読みます。
二十四節気では「清明」から「穀雨」へと移りました。牡丹華は、穀雨の最後の七十二候「末候」です。
いまの4月30日~5月4日ころになります。
七十二候は、自然に寄り添う暮らし方の知恵を紹介してくれています。
そのなかでも、EATでは旬の食材についてご紹介しています。自然にそった食べ方の参考にしていただけると嬉しいです。
二十四節気「穀雨(こくう)」
穀雨とは、穀物を育み、草木をうるおす春の雨が降るころのことをいいます。
春季の最後の節気となります。穀雨の終わりに、八十八夜が訪れます。
七十二候「牡丹華(ぼたんはなさく)」

新暦で4月30日~5月4日ころ。
晩春。牡丹の花が咲きはじめるころ。
陽ざしに透けてふんわりと重なる花びらが美しい牡丹。
中国では牡丹は花の王などと呼ばれ、愛でられ、華やかさの象徴とされてきました。
この時期、八十八夜(立春の日から数えて八十八日目の夜)が訪れます。農の吉日とされて、種を蒔いたり、茶摘みをする季節です。この時期に摘まれた新茶は長寿の薬といわれたそうです。若々しく爽やかな新茶は、心にも体にもやさしくしみわたるでしょう。
旬の食材「こごみ」

こごみの正式名称は「クサソテツ」といい、多年生のシダ植物です。新芽の先端が渦巻き状になっており、人が屈みこんだ姿に似ていることから名づけられたといわれています。地下の株は越冬し、春~初夏に渦巻き状に丸まった新芽がでてきます。
3月から5月にかけてが旬です。
こごみには、ほとんどどアクはなく、味の癖もあまりありません。ぬめりのある触感がおいしい山菜です。ほろ苦い山菜が苦手な方にもおすすめです。
水で洗うだけで下処理は完了です。
採りたては生でも食べられます。天ぷらにしたり、塩ゆでしおひたしにするものおすすめです。
こごみには不溶性食物繊維が豊富に含まれています。不溶性食物繊維には腸の動きを活発にし、体に有害な物質を体外へ排出する働きもあります。
旬の食材は栄養価も高く、一番おいしいとき!
皆さんはこごみで何を作りますか?
「身土不二」暮らす土地の旬の食材をたくさんいただきたいですね!!
| 【七十二候とは】 日本には、一年を4つに分けた「春夏秋冬」のほかに、一年を24等分し季節を表す「二十四節気」、さらに細かく一年を72等分した「七十二候」という暦があります。 七十二候は、四季折々のできごとをそのまま名前にしていて、5日ごとに新しい季節に移ります。 日本人は昔から、七十二候を田植えや稲刈りなど農耕の目安にし、節分やお彼岸、土用など季節の節目を知る暦として使っています。今では私たちの暮らしの中に溶け込み、馴染み深いものも少なくありません。また、七十二候では、植物や生き物たち、旬の食材などが紹介され、こまやかな季節の移ろいを感じるとることができます。 気候変動によって気候の変化も大きい現代には、少しずれているところもあるかもしれませんが、自然に寄り添う暮らしを思い出させてくれる知恵がいっぱいつまっています。 |
参考:白井明大・有賀一広(2020)『日本の七十二候を楽しむー旧暦のある暮らしー』角川書店.
写真=pixabay
文=板倉由佳