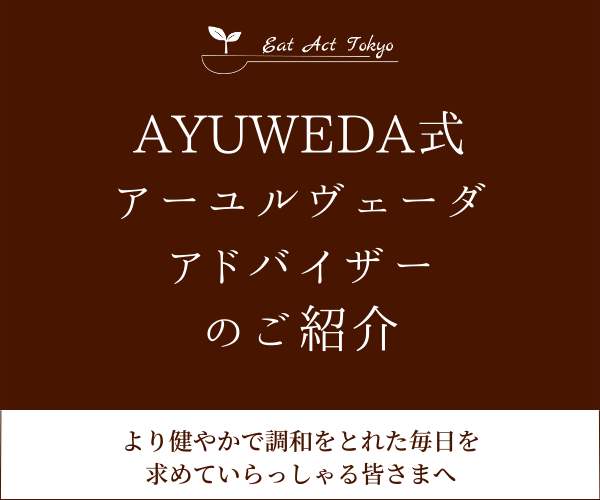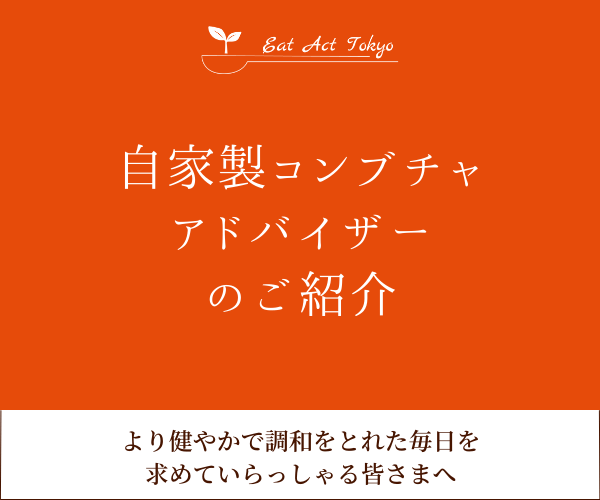今回は、自然にそった暮らし、七十二候の第五候「霞始靆」について。
霞始靆は、「かすみはじめてたなびく」と読みます。
七十二候は雨水の「初候」土脉潤起から「次候」霞始靆へ移りました。
霞始靆は、いまの2月24日~28日ころになります。
七十二候は、自然に寄り添う暮らし方の知恵を紹介してくれています。
そのなかでも、EATでは旬の食材についてご紹介しています。自然にそった食べ方の参考にしていただけると嬉しいです。
二十四節気「雨水(うすい)」
雨水とは、降る雪が雨に変わり山の雪、氷が解けだすころのことをいいます。
昔から農耕の準備をはじめるころとされています。
七十二候「霞始靆(かすみはじめてたなびく)」

新暦で2月24日~28日ころ。
まだまだ寒い日もある2月。この頃になると気温も少しずつ上がり、遠くの景色が白くぼんやり見える日があります。霞が棚引く(たなびく)とは、まさにそんな風景。
霞は春に使われる言葉、現象をいいます。春以外の季節では、霧とも靄(もや)と呼ばれます。
「たなびく」とは霞に使われ、霧は「立ちこめる」「かかる」などと表現します。
2月も終盤。世の中は、受験やまもなく迎える卒業、転勤など、年度末・節目が近づき慌ただしくなる時期ですが、そんなときこそ霞たなびく美しい景色を見て癒され、ホッと一息春を感じる時間を大切にしたいですね。
※靆(たなびく)は昔使われていた漢字で、霞が層をなして横引きに漂う様子をいいます。今は「棚引く」と書くのが一般的です。
旬の食材「からし菜」

からし菜はアブラナ科の野菜。キャベツや白菜の仲間で、2月~4月が旬です。
古くに中国から渡ってきたからし菜は、その名のとおり種はからしの原料となります。葉はわさびと似たようなツンと辛さがあります。
生でちぎってサラダにいれたり、和え物にしたり、炒めたりと楽しめ、特有の苦みと辛さがいろいろな料理のアクセントになります。
同じアブラナ科のキャベツや白菜と比べマイナーな野菜ではありますが、比較的どこでも手に入りやすい野菜です。
非常に栄養価も高く、葉酸、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄分などのミネラルに加えて、ビタミンKやβカロテンなどのビタミン類も豊富に含んでいます。抗酸化力、免疫力を高める作用が期待できる栄養素がいっぱいです。
からし菜の辛味は「アリルイソチオシアネート」という成分で、優れた抗菌力を持っています。そのため食中毒予防の効果も期待できます。また、この辛み成分には、唾液の分泌を促してくれる働きもあるため、消化促進も期待できます。
【おすすめの調理法】
- からし菜をよく洗い、葉についている土や虫をきれいに落とします。
- その後、沸騰直前のお湯で湯通しし、塩もみしておきます(すぐに使わない場合は、このまま冷凍か冷蔵保存する)。
それを、お漬物や和え物などにするとおいしくいただけます。
辛味や苦みがあるお野菜なので小さなお子さんには不向きですが、炒め物にもサラダにも何にでも適している葉野菜です。
旬の食材は栄養価も高く、一番おいしいとき!
皆さんはからし菜で何を作りますか?
「身土不二」暮らす土地の旬の食材をたくさんいただきたいですね!!
| 【七十二候とは】 日本には、一年を4つに分けた「春夏秋冬」のほかに、一年を24等分し季節を表す「二十四節気」、さらに細かく一年を72等分した「七十二候」という暦があります。 七十二候は、四季折々のできごとをそのまま名前にしていて、5日ごとに新しい季節に移ります。 日本人は昔から、七十二候を田植えや稲刈りなど農耕の目安にし、節分やお彼岸、土用など季節の節目を知る暦として使っています。今では私たちの暮らしの中に溶け込み、馴染み深いものも少なくありません。また、七十二候では、植物や生き物たち、旬の食材などが紹介され、こまやかな季節の移ろいを感じるとることができます。 気候変動によって気候の変化も大きい現代には、少しずれているところもあるかもしれませんが、自然に寄り添う暮らしを思い出させてくれる知恵がいっぱいつまっています。 |
参考:白井明大・有賀一広(2020)『日本の七十二候を楽しむー旧暦のある暮らしー』角川書店.