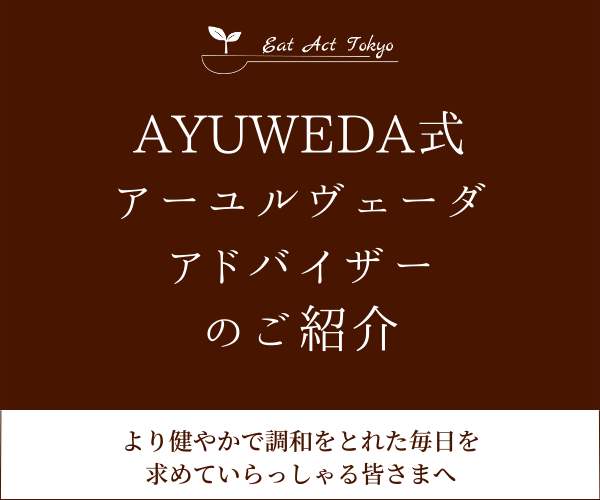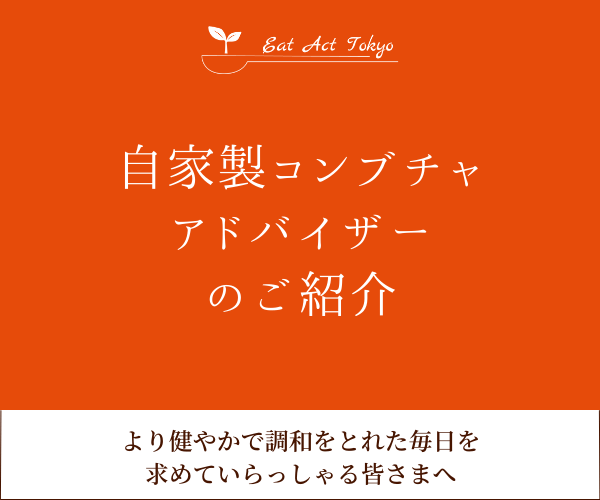今回は、自然にそった暮らし、七十二候の第六十三候「鱖魚群」について。
鱖魚群は、「さけのうおむらがる」と読みます。
七十二候は大雪の次候「熊蟄穴」から末候「鱖魚群」へ移りました。
いまの12月16日~20日ころになります。
七十二候は、自然に寄り添う暮らし方の知恵を紹介してくれています。
そのなかでも、EATでは旬の食材についてご紹介しています。自然にそった食べ方の参考にしていただけると嬉しいです。
二十四節気「大雪(たいせつ)」
大雪とは、真冬が訪れ、まさに大雪が降り積もるころのことです。
北国では、降り積もった雪が春まで溶けずに残る「根雪(ねゆき)」となる雪が降ってきます。
七十二候「鱖魚群(さけのうおむらがる)」

新暦で12月16日~20日ころ。
鱖魚群とは、川で生まれ育った鮭が海で大きくなり、産卵のために群れでふるさとの川を上るころのことです。
12月16日は念仏の口止めの日です。
諸説ありますが、正月の神様は念仏が嫌いということから、12月16日前後から1月16日(念仏の口明け)ころまでは念仏を唱えないという風習が地方によってはあるそうです。
旬の食材「にら」

にらは1年を通して食べられている食材ですが、冬から春にかけて採れるにらは葉が厚くてやわらかく、香りも濃くなります。
にらは3000年以上前から中国、インド、モンゴルなどで栽培され、日本では弥生時代から食べられていたといわれています。
にらの独特な香りは硫化アリル(アリシン)によるもので、血行促進や殺菌作用の効果、疲労回復などが期待できます。また食欲を増進してくれるといわれています。
にらを加熱する際は、油とともに炒めるとアリシンが分解されにくい状態になるのでおすすめです(加熱に弱いアリシンは油と調理することで分解されにくくなります)。
また、にらにはβ-カロテン、ビタミンCも豊富です。
にらの選び方:
葉にツヤがあり濃い緑色のもの、葉が折れていないもの、切り口がみずみずしいもの、手で根元を持った時にピンと立ち、大きく曲がらないものを選びましょう。
旬の食材は栄養価も高く、一番おいしいとき!
皆さんはにらで何を作りますか?
「身土不二」暮らす土地の旬の食材をたくさんいただきたいですね!!
| 【七十二候とは】 日本には、一年を4つに分けた「春夏秋冬」のほかに、一年を24等分し季節を表す「二十四節気」、さらに細かく一年を72等分した「七十二候」という暦があります。 七十二候は、四季折々のできごとをそのまま名前にしていて、5日ごとに新しい季節に移ります。 日本人は昔から、七十二候を田植えや稲刈りなど農耕の目安にし、節分やお彼岸、土用など季節の節目を知る暦として使っています。今では私たちの暮らしの中に溶け込み、馴染み深いものも少なくありません。また、七十二候では、植物や生き物たち、旬の食材などが紹介され、こまやかな季節の移ろいを感じるとることができます。 気候変動によって気候の変化も大きい現代には、少しずれているところもあるかもしれませんが、自然に寄り添う暮らしを思い出させてくれる知恵がいっぱいつまっています。 |
参考:白井明大・有賀一広(2020)『日本の七十二候を楽しむー旧暦のある暮らしー』角川書店.